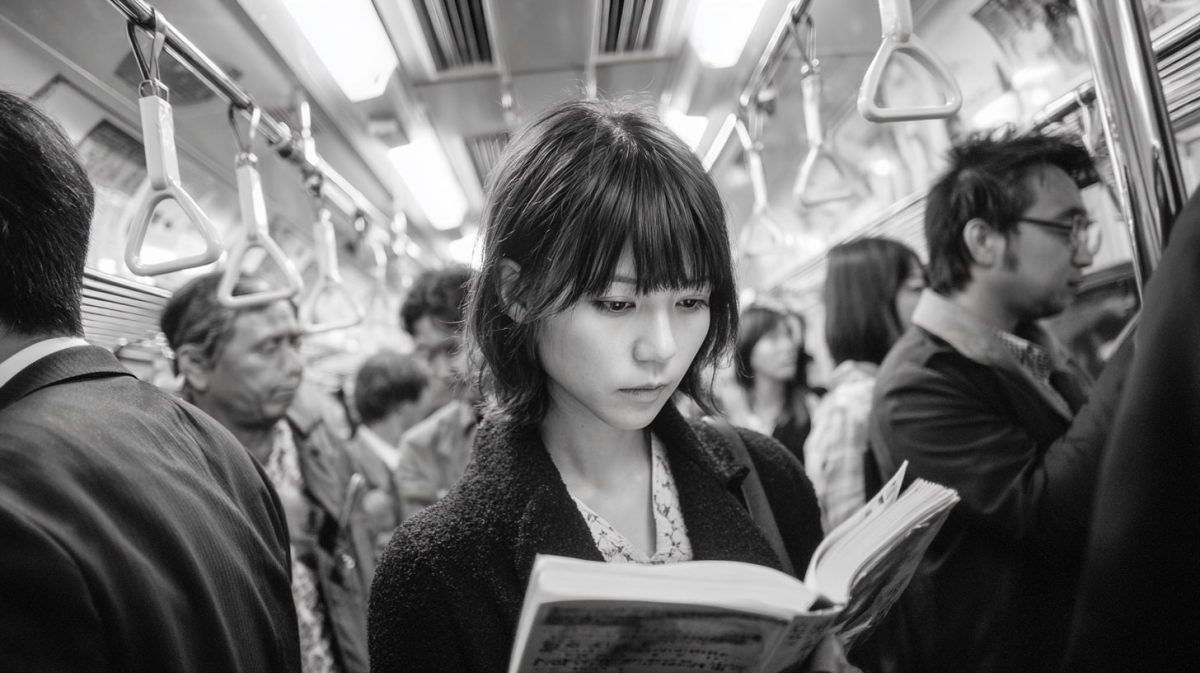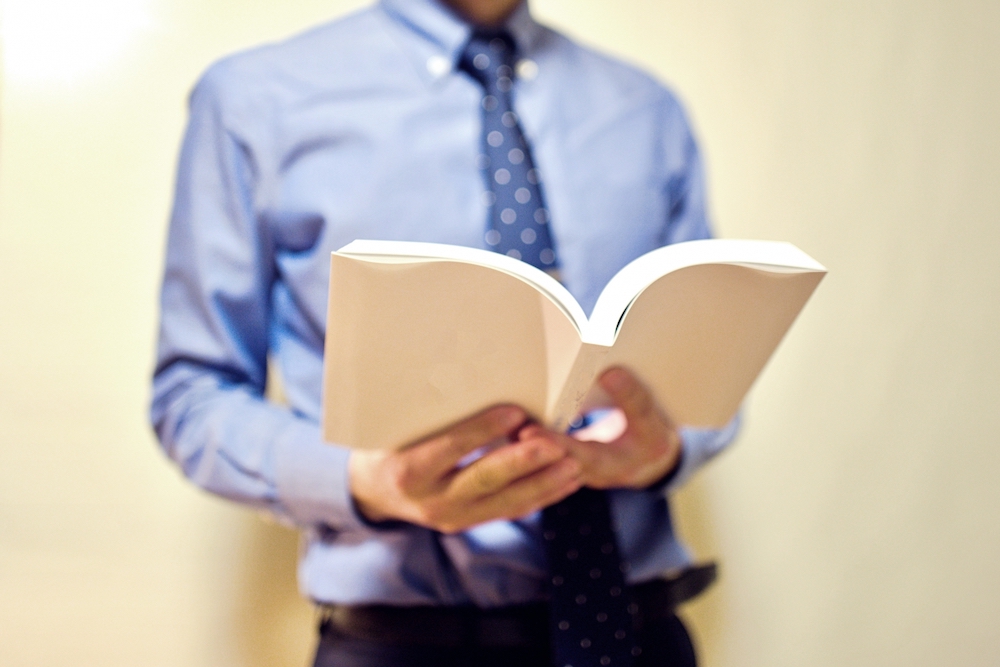「時間がない…」
働きながら社労士を目指すあなたも、きっと一度はそう感じたことがあるはずです。
何を隠そう、4年前の私もそうでした。
4年間の受験生活、最初の3年間はまさに「時間がない」ことを言い訳に、何度も何度も挫折しかけました。
でも、ある一つの考え方に変えたことで、ついに4年目にして合格を掴むことができたんです。
この記事では、特別な才能も十分な時間もなかった私が、どうやって勉強時間を捻出し、合格までたどり着いたのか。
その「唯一の方法」を、私のたくさんの失敗談と共にお伝えします。
この記事を読み終える頃には、あなたはもう「時間がない」とは言わなくなっているはずです。
関連: 社会保険労務士 杉並区
なぜ「時間がない」と感じてしまうのか?- 私がハマった3つの罠
合格した今だからこそ分かりますが、以前の私は「時間がない」のではなく、貴重な時間を無駄にしてしまう「罠」にハマっていただけでした。
あなたも、もしかしたら同じ罠にハマっているかもしれません。
罠1:完璧主義でインプットばかりしていた1〜2年目
最初の頃の私は、とにかく真面目でした。
テキストの隅から隅まで、一言一句理解しないと次に進めなかったんです。
「完璧に理解してから問題集を解こう」
そう思っているうちに、1冊のテキストを終えるのに数ヶ月…。
気づけば、最初の方にやった内容はすっかり忘れてしまっていました。
インプットに時間をかけすぎた結果、最も重要なアウトプット(問題を解くこと)の時間が全く足りなくなってしまったのです。
勉強時間は確保しているのに、全く成果に繋がらない。
そんな焦りだけが募る毎日でした。
罠2:「ながら勉強」で集中力が分散していた日々
仕事から疲れて帰ってきて、まとまった勉強時間をとるのは本当に大変ですよね。
私もそうでした。
だから、「テレビを見ながらテキストを読もう」「好きな音楽を聴きながらアプリで問題を解こう」と、いわゆる「ながら勉強」をしていたんです。
自分では勉強しているつもりでした。
勉強した「時間」だけを見て、今日も頑張ったな、と満足してしまっていたんです。
でも、実際は全く頭に入っていませんでした。
集中力が分散して、勉強の質が著しく低下していたことに、当時の私は気づけなかったのです。
罠3:他人と比べて焦り、計画が崩壊した3年目
3年目になると、さすがに焦りが出てきます。
そんな時、つい見てしまうのがSNSでした。
「模試でA判定でした!」
「今日は10時間勉強しました!」
キラキラした報告を見るたびに、「それに比べて自分は…」と落ち込み、自分のペースを見失っていきました。
「あの人に追いつかなきゃ」という焦りから、無謀な学習計画を立てては、達成できずに自己嫌悪に陥る。
まさに、負のスパイラルでした。
他人と比べることで生まれた焦りは、私の心をすり減らし、貴重な勉強時間さえも奪っていったのです。
私が4年目で見つけた唯一の方法「時間ポートフォリオ戦略」
3年間の失敗を繰り返し、もうダメかもしれないと思った時、私はふと気づきました。
「私に足りないのは、時間そのものではない。時間の使い方なんだ」と。
そこから生まれたのが、合格を掴み取る唯一の方法となった「時間ポートフォリオ戦略」です。
「時間がない」のではなく「時間の使い方が間違っている」という発見
「時間がない」と嘆いている時、私たちは時間に対して受け身になっています。
まるで、時間は誰かから与えられるもので、自分ではコントロールできないかのように。
でも、4年目に私は考え方を変えました。
「時間は自分で創り出すものだ」と。
このマインドセットの転換が、全ての始まりでした。
時間は有限な資産であり、それをどう配分するかは自分次第。
金融資産のポートフォリオを組むように、自分の時間も戦略的に配分する必要がある。
そう気づいたのです。
時間を4種類に色分けして、やるべきことを最適化する
時間ポートフォリオ戦略はとてもシンプルです。
まず、1日の時間を以下の4種類に色分けします。
- まとまった集中時間(ゴールド時間✨):静かな環境で、誰にも邪魔されずに2〜3時間集中できる時間。
- スキマ時間(シルバー時間🥈):通勤電車の中や昼休み、待ち合わせなどの5分〜15分の細切れ時間。
- ながら時間(ブロンズ時間🥉):家事をしている時や、お風呂に入っている時など、耳は空いている時間。
- 休息時間(リフレッシュ時間🌿):勉強から完全に離れて、心と体を休める時間。
そして、それぞれの時間の特性に合った勉強を割り当てるだけです。
例えば、思考力が必要な過去問演習は「ゴールド時間」に。
暗記が中心の一問一答アプリは「シルバー時間」に。
講義の音声学習は「ブロンズ時間」に。
こうすることで、無理なく、無駄なく、全ての時間を勉強に最適化できるようになったのです。
「やらないこと」を決める勇気
時間ポートフォリオ戦略のもう一つの重要なポイントは、「やらないこと」を決める勇気を持つことです。
完璧主義だった私は、出題頻度の低いマイナーな論点や、誰も解けないような難問にも時間をかけていました。
でも、社労士試験は満点を取る必要はありません。
合格点を取ればいいんです。
4年目にして、私は勇気を出して「やらないこと」を決めました。
具体的には、「過去10年で1度しか出ていない論点は深追いしない」「正答率20%以下の難問は捨てる」といったルールです。
この「捨てる勇気」が、本当にやるべき重要な論点に集中するための時間を生み出してくれたのです。
【完全公開】合格した年の私の1週間タイムスケジュール
「時間ポートフォリオ戦略」を、私が実際の生活にどう落とし込んでいたのか。
合格した年の、ある1週間のリアルなタイムスケジュールを公開します。
ぜひ、あなたの生活に当てはめてみてください。
平日のタイムスケジュール(月〜金)
| 時間帯 | 行動 | 時間の種類 | 勉強内容 |
|---|---|---|---|
| 6:00-7:00 | 起床・準備 | ゴールド時間✨ | 前日の復習、択一式問題演習(10問) |
| 7:30-8:30 | 通勤(電車) | シルバー時間🥈 | 一問一答アプリ、テキスト読み込み |
| 12:00-13:00 | 昼休み | シルバー時間🥈 | 選択式問題の穴埋め練習 |
| 19:00-20:00 | 帰宅(電車) | シルバー時間🥈 | 一問一答アプリ、その日のニュースチェック |
| 20:00-21:00 | 夕食・入浴 | ブロンズ時間🥉 | 講義の音声学習(1.5倍速) |
| 21:00-23:00 | 自由時間 | ゴールド時間✨ | その日一番のメイン学習(過去問演習など) |
| 23:00-24:00 | 自由時間 | リフレッシュ時間🌿 | 読書やストレッチなど、勉強以外の時間 |
休日のタイムスケジュール(土日)
休日は、平日に不足しがちな「ゴールド時間」を確保する最大のチャンスです。
ただし、一日中勉強するのではなく、必ずリフレッシュの時間も計画に組み込むのがポイントです。
| 時間帯 | 行動 | 時間の種類 | 勉強内容 |
|---|---|---|---|
| 7:00-8:00 | 起床・朝食 | – | – |
| 8:00-11:00 | 午前勉強 | ゴールド時間✨ | 過去問演習(1年分)、苦手分野の集中学習 |
| 11:00-13:00 | 休憩・昼食 | リフレッシュ時間🌿 | 散歩や買い物など、外に出て気分転換 |
| 13:00-16:00 | 午後勉強 | ゴールド時間✨ | 模試の解き直し、法改正点の確認 |
| 16:00-18:00 | 自由時間 | リフレッシュ時間🌿 | 友人や家族との時間、趣味の時間 |
| 20:00-22:00 | 夜勉強 | ゴールド時間✨ | 1週間の総復習、翌週の計画立て |
このように、生活のあらゆる時間を色分けし、パズルのように最適な勉強をはめ込んでいく。
これが、私が時間を創り出した方法です。
4年間勉強を続けられたモチベーション維持術
とはいえ、4年という長い期間、常に高いモチベーションを保てたわけではありません。
何度も心が折れそうになりました。
そんな時、私を支えてくれた3つの工夫をご紹介します。
SNSは「仲間を見つける」ツールとして活用する
3年目に私を苦しめたSNS。
4年目には、その使い方を180度変えました。
他人と比べて落ち込むのではなく、「励まし合える仲間を見つける」ツールとして活用したのです。
「今日はここまで頑張った」「この問題が分からない」と発信すると、同じように頑張る仲間から「いいね」やコメントが届きます。
その一つひとつが、「一人じゃないんだ」という心強い支えになりました。
SNSは、使い方次第で最高の味方になってくれます。
小さな目標達成を可視化する「合格カレンダー」
長期的な勉強では、日々の成長が感じにくく、やる気を失いがちです。
そこで私は、とても簡単な工夫を始めました。
それは、100円ショップで買った大きなカレンダーに、その日勉強した時間を書き込み、目標を達成できたらシールを貼る、というものです。
月末に、シールで埋まったカレンダーを眺めるのが、私の密かな楽しみでした。
「今月もこんなに頑張ったんだ」
そんな日々の小さな達成感を可視化することが、ゴールまでの長い道のりを歩き続けるための、大切なガソリンになってくれました。
「なぜ社労士になりたいのか」原点に立ち返る時間を作る
それでも、どうしても心が折れそうになる時があります。
そんな時は、無理に机に向かわず、静かなカフェに行ってノートを開きました。
そして、「私は、なぜ社労士になりたいんだろう?」と、自分の心に問いかけるんです。
私が社労士を目指したきっかけは、前職で労働問題に悩む同僚を助けられなかった悔しさでした。
「専門知識があれば、あの人を守れたかもしれない」
「働く人が、もっと安心して輝ける社会を作りたい」
その原点を思い出すたびに、胸が熱くなり、「よし、もう一度頑張ろう」と自然に思えました。
あなたも、心が折れそうになったら、ぜひ原点に立ち返る時間を作ってみてください。
よくある質問(FAQ)
ここでは、私がSNSなどでよくいただく質問にお答えします。
少しでもあなたの不安が解消されれば嬉しいです。
Q: 通信講座と独学、どちらがおすすめですか?
A: 4年間の経験から両方の視点でお答えしますね。
最初の2年間は独学でしたが、情報の取捨選択に時間がかかり、非効率だったと反省しています。
3年目から通信講座を利用し、カリキュラムに沿って進めることで学習のペースが掴みやすくなりました。
ご自身の状況に合わせて、まずは色々な講座の資料請求から始めてみるのがおすすめです。
Q: 模試の点数が伸び悩んでいます。どうすればいいですか?
A: その気持ち、痛いほど分かります!私も3年目の模試はずっとE判定でした。
でも、今なら言えます。点数に一喜一憂せず、「弱点発見のツール」と割り切ることが本当に大切です。
間違えた問題こそが、合格への近道を示してくれる宝物。
その一問を完璧に理解することに集中しましょう。
Q: 家族やパートナーの協力はどうやって得ましたか?
A: これはとても重要ですよね。
私は「なぜこの資格を取りたいのか」「いつまでに合格したいのか」を具体的に伝え、自分の本気度を分かってもらう努力をしました。
その上で「この1年だけ、どうか集中させてほしい」と正直にお願いし、家事の分担などを具体的に相談しました。
そして、感謝の気持ちを言葉で伝えることを絶対に忘れないようにしていました。
Q: 勉強がどうしても嫌になった時の対処法は?
A: 思い切って、1日完全に勉強から離れることです!
私も実際にやりました。罪悪感を感じる必要は全くありません。
リフレッシュして「また明日から頑張ろう」と思えれば、その1日は未来への最高の投資です。
嫌々机に向かう10時間より、ずっとずっと効率的ですよ。
Q: 4年も勉強を続けて、心が折れませんでしたか?
A: 正直に言うと、何度も、数え切れないくらい折れました。
でもその度に、「ここで諦めたら、今までの3年間が全部無駄になる」と思い直しました。
そして、SNSで同じように頑張る仲間を見て「私だけじゃない」と自分を奮い立たせていました。
諦めなければ、必ず道は開けます。これは、4年かかった私が保証します。
まとめ
「時間がない」
それは、かつての私自身が最も頼りにしていた、そして最も自分を苦しめていた言い訳でした。
しかし、時間を「管理する」という受け身の姿勢から、「自ら創り出す」という能動的な視点に変えたとき、合格への道がはっきりと見えてきました。
この記事でお伝えしたことを、最後にまとめます。
- 「時間がない」と感じるのには、完璧主義や他人との比較といった「罠」がある。
- 時間を4種類に色分けし、最適な勉強を割り当てる「時間ポートフォリオ戦略」を実践する。
- 合格点をとるために「やらないこと」を決める勇気を持つ。
- SNSやカレンダーを活用し、日々のモチベーションを維持する工夫をする。
- 辛い時は「なぜ社労士になりたいのか」という原点に立ち返る。
4年という時間は、決して短い道のりではありませんでした。
しかし、その失敗と試行錯誤の全てが、今の私の財産です。
この記事で紹介した私の経験が、かつての私と同じように悩み、もがいているあなたの助けになれば、これほど嬉しいことはありません。
あなたには、あなただけの戦い方があります。
諦めずに、自分を信じて、合格を掴み取ってください。
心から応援しています!
私のSNSでは、日々の勉強の気づきや、受験生の皆さんからの質問にもっと気軽にお答えしています。
一緒に頑張る仲間を見つけたい方、ぜひフォローしてくださいね!
私が実際に使っていたスケジュール表のテンプレートも限定配布中です。